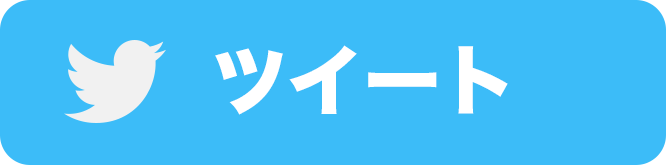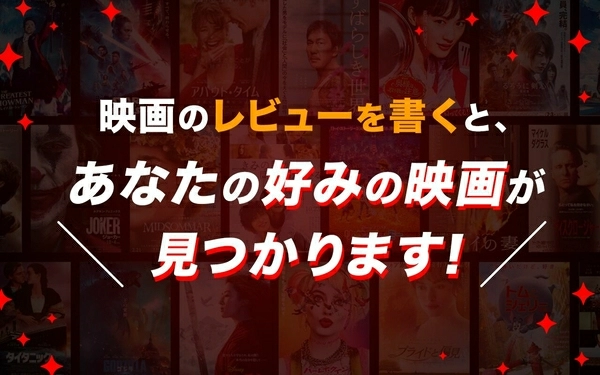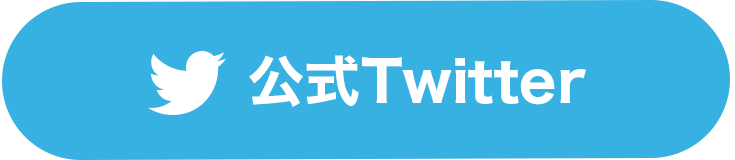選挙と鬱の町山智浩さんの解説レビュー
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
映画評論家の町山智浩さんがTBSラジオ『こねくと』(https://www.tbsradio.jp/cnt/)で、『選挙と鬱』のネタバレなし解説を紹介されていましたので書き起こしします。
映画視聴前の前情報として、また、映画を見た後の解説や考察レビューとして是非ご参考ください。
町山さん『選挙と鬱』解説レビューの概要
①映画『選挙と鬱』を作るキッカケは町山さんだった
②青柳監督は奨学金返済中で四畳半の家に住んでいる
③水道橋博士の2022年の○○を追ったドキュメンタリー映画
④選挙出馬のきっかけはスラップ裁判を広く知ってもらう為だった
⑤1度はハッピーエンドで完成した映画だったが
⑥鬱になり議員をやめてしまい映画の公開ができなくなってしまった
※○○の中に入る文章は、この記事の1番最後で公開しています。
TBSラジオたまむすびでラジオ音源を聞いて頂くか、書き起こし全文をご覧頂くか、この記事の1番最後を見て頂く事で判明します。
『選挙と鬱』町山さんの評価とは
(町山智浩)今日はまぁゲストをスタジオに急にお呼びしました。いらっしゃってますね。水道橋博士とですね映画監督の青柳拓監督なんですが、この2人が・・コンビじゃないな。(笑)作った映画がですね今週土曜日公開ですか。『選挙と鬱』というドキュメンタリー映画なんですがそれを今日はご紹介します。博士と監督よろしくお願いします。
(青柳拓)よろしくお願いします。
(水道橋博士)よろしくお願いします。
(石山蓮華)よろしくお願いいたします〜スペシャルゲストです。
(水道橋博士)youtubeでいつもやってるんですけど。なんかね。
(でか美ちゃん)違いますか?
(水道橋博士)違いますね。しかも青柳監督はTBSに入る事自体が生まれて初めてなんですって。
(青柳拓)お城みたいなね、これすごいですね!
(でか美ちゃん)そんなきらびやかではないですが。(笑)
(石山蓮華)お城みたいな所からお届けしております。(笑)あの水道橋博士にはですね、青柳監督にも『こねくと』宛てにコメントを頂戴した事があるんですが、こうしてスタジオで顔を合わせてお話しさせてもらうのは初めてという事で。
(水道橋博士)蓮華さんは僕初めてなんですよ。でか美ちゃんは2代目水道橋博士として、僕のキャリアを全部追っかけてきてるという。
(でか美ちゃん)違います。やめてやめてって本人の前で言うのもアレですけど。私はですね、BS12トゥエルビという局でやっている『BOOKSTAND.TV』という本をご紹介する番組、2代目MCでして、初代が博士なんですよ。で、なぜ私が2代目になったかというと、博士が政治家になったからという理由ですごく私的にも、ちょっとこう『選挙と鬱』という作品はつながりを感じるもので、でその『BOOKSTAND.TV』にも青柳監督に来ていただいた事あるので、私はお2人ともお会いした事あるという形で。ありがとうございます。
(青柳拓)バックボーンがあってですね、呼んでいただけたので。
(水道橋博士)で、その『選挙と鬱』っていう映画を作るきっかけになってんのは町山さんからなんですね。
映画『選挙と鬱』を作るキッカケは町山さん
(青柳拓)まさに。
(石山蓮華)町山さん、そもそもなんですが、私もね『選挙と鬱』実は試写で拝見したんですけども。映画の話が出るきっかけが町山さんでしたね。
(町山智浩)そうですね。これ、何年前ですか、もう2022年ですか。
(水道橋博士)3年前です。
(町山智浩)ちょうど今ぐらい?6月ですよね。
(水道橋博士)しかもまた、3年後の今参院選が始まるところですからね。
(町山智浩)そうですよね。で、参院選の選挙の時にね、博士が立候補する事になって、博士と話してて。その時、なんというか月に1回ぐらい雑談してたんで博士と。Zoomでね。で、これはね、やっぱり全部ドキュメンタリー撮った方がいいんじゃないかと。カメラを入れて全部記録した方がいいんじゃないかと僕が言って。で、青柳監督に直接僕がお願いしたと。
(水道橋博士)指名したんですよ。公募しておいて指名してるんですよ。
(石山蓮華)そうそう。その流れを見てて思いましたけれど。
(でか美ちゃん)ありなのかそれはって。
(青柳拓)前作の『東京自転車節』っていう映画を見てくださってたんですよね、それで声をかけてくれる経緯があったという事でありがとうございます。

(水道橋博士)まだ29歳だったから。で、一応制作会社がついてYouTubeをやってたので、テレビのスタッフもいるんですよ。そしたら、その制作会社に乗り込んで。
(石山蓮華)青柳さんが。
(水道橋博士)えぇ。ファイナルカット権をください。制作費も全部出しますって。
(青柳拓)そこはがっつり言わせていただきましたけど、受け入れてくださって。
(水道橋博士)20代の子がこういうのを言うと、その制作会社の社長もちょうど60、僕も町山さんも60で。その言やよしなんですよ。それを待ってた!っていうぐらいな感じで。
(青柳拓)普通はね怒られるかもしれないんですけど。でもやっぱり町山さんと博士ですからそこは分かってくださって。
(水道橋博士)町山さん、しかも作品を見てたから。ちゃんとしたものができるっていうのは分かってて。僕はまだ見てなかったから。でもそのうちに次第に彼が、俺制作会社を持ってる映画監督だと思ってたら、東中野の4畳半で風呂なしに住んでるっていうのが分かって。なんちゅう大胆な事をしたんだって。
青柳監督は奨学金返済中で四畳半の家に住んでいる
(でか美ちゃん)そこのね、こうその選挙というものに対する興味が、自分は奨学金を返さなきゃいけないっていうその青柳監督の立場から始まるっていうのもすごい・・4畳半っていうのもそうかと思いました今。あまり意外ではなかったです私からしたら。(笑)
(石山蓮華)奨学金が550万円あった・・。今もそれありますか奨学金。
(青柳拓)今もありますね。返していって。で、本当大学生の2人に1人はね、借りているという状況で。
(石山蓮華)私も借りてました。
(水道橋博士)あ、そうですか。
(町山智浩)僕も借りてました。
(青柳拓)結構社会的な状況ですからこれは。大体300万ぐらい平均借りてるっていう。
(石山蓮華)そうですね。私も大体300万円くらい大学を卒業したタイミングで奨学金という借金を負っていたんですけれども。まぁ今ね、たまたま返せましたが、監督は、町山さんからこうやってこうきっかけでお話をいただいて。撮るぞってなった時。どういう気持ちだったんですか?
(青柳拓)いや〜だから僕は初めての選挙っていうか、選挙には興味という意識はなかったんです。そんなにね。
(水道橋博士)あんまりポリティカルな人じゃなかったから。もちろん福祉とか、その辺の事はすごく作品としてテーマに挙げていたけど。政治とか政局とか、そういう事に興味がある人じゃなかったから。
(青柳拓)でもまぁ僕にとってはまぁ初めての事だったけど選挙ってそもそもね、どんな人にでも当事者ですから。自分ごとに持ってこれれば、絶対面白い映画になるんだろうなっていうのはわかったので。もう自分に必然性があると思って、ガッツンと行っていけば、その過程の獲得の姿が面白い映画になるんじゃないかなという風に思って、はい。決めました。
水道橋博士の2022年の選挙を追ったドキュメンタリー映画
(水道橋博士)『東京自転車節』っていう前作が疾走感のある映画、ロードムービーだったんですけど。そのカメラを持つスピードとか、ストーリーを転がしていく力っていうのはあるんだっていうのは見て分かってたから。あとはお任せで完全に24時間体制で、1ヶ月半、チームの中にいましたね。
(石山蓮華)ねぇ。で、その青柳監督の溶け込む力というか。そのこう、今ね、こうやってラジオでお話しされててもニコニコとして。
(でか美ちゃん)口角がキュッと上がってね。
(石山蓮華)やわらかい。
(でか美ちゃん)笑顔以外の顔、見た事なくて私、逆に怖いんですよ。青柳監督。(笑)
(石山蓮華)私もね、この映画を試写で拝見して、ちょっと怖いなと思ったのが、青柳さんがその人の良さというか、人当たりの柔らかさと、この真っすぐな視点っていうもので、どこまでも真っすぐに入っていくっていうのがすごいなって。これトイレのシーンもあるんですよね。
(青柳拓)えぇそうですね。それは本当に博士さんがやっぱり開いてくれたからですね。最初に本当に24時間誰でもいつでも撮っていいよ。著作権フリーだからって言ってくれたんですよ。僕、見ず知らずの人間ですよ。なのにこうやって声をかけてくれて開いてくれたっていう。そこにやっぱり感謝というか希望を持ってそこに貫いていったら最後、トイレのシーンというのがなんか、関係性の結実っていう感じでかなり良かったなと。
(水道橋博士)僕も博士っていう名前と、また鬱のイメージもあるから、すごい気難しい人に見られるかもしれないけど。本当僕、結構オープンなんですよ。人が泊まるのもいい。外国人が来るのもいい。どういう風に・・プライベート自分のいらないぐらいな感じ。だから全然そこはね、来るなら24時間回してっていう感じで。一緒に飲み食いし、お風呂に最後は行くっていうね。
(でか美ちゃん)私もコメントを寄せさせてもらいまして、映画を見てるんですけど。やっぱりドキュメンタリーとしてずっと追ってく中で、正直まさか当選するとはとか、その後の鬱の展開とかって、もう映画のネタバレというよりはちょっと皆さんね、博士の事を追っていたらご存知の事かと思うんですけど。
(水道橋博士)タイトルを見ても分かるしね。
(でか美ちゃん)そうそう、タイトルそのままですし。青柳監督からしたら、ちょっとカメラ回しづらい状況っていうのは続いた気がしたんですよ。正直、本当に失礼だけど落選の方がオチがつく映画だったじゃないですか。最初の頃を考えたら。
(水道橋博士)そうだと思ってたしね。
(でか美ちゃん)どうだったんですか?
選挙に落選の方が落ちがついたのでは?
(青柳拓)いや最初そうでした。本当に博士、わかりますかね、あのミッキー・ロークの『レスラー』っていう映画があるんですけど。過去の栄光を極めたレスラーがもう1度立ち上がってボロボロになりながらもリングに立つみたいな。それでラスト、結構悲しいラストというか、希望があるラストというか。結構負けのラストっぽいんですよ。それをイメージしてたんですよね。博士の姿に。
(でか美ちゃん)なんならね、その想定で。(笑)
(青柳拓)それでいったら、なんだ、だんだん博士が本気になっていくっていうのが分かってきて、有権者の人達と声かかって。そのなんか過程を見ていくと、あれ?わからないぞみたいな。これいくんじゃないかいけないんじゃないかって。
(水道橋博士)比例区で出たんで、地方の惨状を見る訳ですよ。で、そこで話し合いが必ずあるので、そこをやっていくうちに、本気スイッチが入りましたね。だから東京にいると、東京にももちろんつらい立場の人も苦しい人もいるんだけど。もっともっと広く見えて。しかも、うわこんなに惨状広がってて、政治家っていうのは何ができるのかっていう事を、自分の中に使命を抱くように、それは途中からなっていますね。
(石山蓮華)じゃ、最初は出馬はそのある種きっかけでしか?
(水道橋博士)裁判があったんで。その裁判を松井一郎さんとの裁判がスラップ裁判だという事を、裁判も可視化されてないので、絶対に多くの人に知ってほしいからっていう動機だけでした。
(石山蓮華)このスラップ裁判についての話が出ましたけど、町山さん、スラップ裁判を、反スラップ訴訟法っていうような法律っていうのはアメリカにはあるんですか?
選挙出馬のきっかけはスラップ裁判を広く知ってもらう為だった
(町山智浩)アメリカが始まりなんで。スラップっていう言葉自体がアメリカから出てきたんで。それはだから大企業とか政治家をジャーナリストが批判した時に、そのジャーナリストを名誉毀損で訴えて黙らせるという事を禁じる法律なんですね。で、連邦ではないんですけど、各州ごとにあって、大体ほとんどの州で禁止されているんですけど、日本ではその法律がないので、政治家がちょっとネットとかで批判されるとそれを訴えて黙らせちゃうんですね。あと企業とかがね。で、これはダメっていう風にできないだろうかっていう話をまずずいぶん前に博士としてたんですよ。これは立法化するしかないよみたいな話があって。
(でか美ちゃん)あまりにもこう、なんだろうな、権力とか何かを得てる人に偏っちゃいますもんね。それがまかり通るんだとしたらね。
(町山智浩)そうなんですよ。裁判って勝っても負けても訴える事自体で、普通の人は訴えられた事でもうダメになっちゃうんですよ。
(石山蓮華)そうですね、裁判ってま、初めのタイミングってすごく勢いがあるというか。これ絶対この相手に勝つんだっていう気持ちがあっても、長期化していくと、だんだんだんだんやっぱり気持ちの面でもお金の面でも、削げていく部分があると思うんですよね。
(水道橋博士)タレントだったらそれは訴えられた事によって、番組に出る事を自粛してくださいとかなるんですね。しかもすごく権力者に対してやってる時は、これは政治的な問題になってますからっていうのでレギュラーを打ち切られるっていう事もあったし。まぁそれも3年として続くから弁護士費用なんかもすごくかかるし。これごく一般の普通の人が、急にこういう事をやられるようになったら、可能性もあったんですね。4000人のリツイートしている人も訴えるっていうような脅しもあったので、それはダメだっていう事で、その事を知らしめたいっていうのが最初の動機ですね。
(石山蓮華)でもこうどんどんどんどん変わっていった様子を、この青柳さんがカメラに収めて、で、その完成した映画っていうのをご覧になって、町山さんはどういう感想を持ちました?
(水道橋博士)2年前に1度完成しましたからね。
(青柳拓)でも町山さん出演者ですからね。
(石山蓮華)そうですね、確かに。
(水道橋博士)いやいやハッピーエンドで終わっていたんですよ。
1度はハッピーエンドで完成した映画だったが
(町山智浩)だからとにかく選挙が、最初、要するに撮ってる訳じゃないですか。で、最初は勝ち目がなかったんだけども、勝てる!っていう方向が出てきた訳ですよ。色々。で、これいけると思って、それで開票の時に、僕が博士と話してるんですよ。それを回してんですよ青柳監督がその場を、現場を。で、当確が出た瞬間、僕は博士と話してるんですよ。
(石山蓮華)見ましたよ映画で。
(町山智浩)その超クライマックスにいたんでね、奇跡ってあるなと思いましたね本当に。
(水道橋博士)それも大ハッピーエンドで終わるはずだったんですよ。
(町山智浩)それで、1回この映画はね、完成してるんです。
(でか美ちゃん)そうですよね。そういうこう演出というか、きっかけの展開みたいなもう、あそこはすごいユニークで好きだったシーンなんですけど。
(青柳拓)もう2022年の段階で完成しました。
(町山智浩)ね。僕、監督から見せてもらって。これでもう全然問題ないっていうね、ハッピーエンドで素晴らしい、爽快感のある負け犬の逆襲みたいなね、感じの映画なんですけど。
(水道橋博士)それも公開したいぐらいですよ。
(町山智浩)そうしたら博士がね、辞めちゃったから。これ公開できないよっていう事態になるんですよ。どうすんの監督っていうね。これ自腹でやってますからね。お金ブチ込んでますからね。
(でか美ちゃん)でもやっぱそこからの博士が鬱になってっていうのは、その密着の仕方もちょっと距離感とかは変わらなかったですか?
鬱になってからの撮影方法
(青柳拓)いや変わりましたね。やっぱりどうやって、その周りの人にも鬱病で悩まれてる人がいるんですけど。やっぱりカメラを向けるっていう事に対してすごく慎重になりました。だから一旦は博士の間合いというか距離を保つためにも、撮影を一旦凍結するというか。封印するという形で取り上げて。だんだんだんだん博士が外に出られるようになったタイミングから、博士もなんていうんでしょう、この鬱病の経験を自分と似たような経験をしている、悩んでる人達に、困ってる人に向けて、家族の人とかにも向けて、この自分の鬱病の経験を伝えたいみたいな事を話してるのを見て、その方向に向かえばいいんじゃないか。この映画のこうスタイルというか、方向性を見いだしてきた段階から、かなりまたアクセルを踏み出して。今度だから、選挙っていうフェーズと、鬱っていうその後のフェーズっていう2つの映画のテイストがね、絡み合ったクロスした映画になったなという感じで。
(水道橋博士)鬱ってなかなか映せないから。自分自身俺は映しててもよかったんだけど。その頃まだなんかオープンにすると色々家族も困るだろうみたいな事もあったから。だけど、そこから彼がUber Eatsを『東京自転車節』でやってて。俺もあれをやりたいと。もう1回再起の物語で自転車に乗りたいんだっていうところから、鬱病を映してても、走るじゃないですか。そこがいいっていう。自分なりに。(笑)
(でか美ちゃん)めっちゃ自画自賛だけどわかりますし。(笑)でもちょっと答えたくなかったらいいんですけど、やっぱその、凍結。制作が止まったみたいな時期っていうのは、だから自転車に乗れるようになる前っていうのは何を考えられてたんですか?
(水道橋博士)それは本当に苦しいですよ。トイレに行くのも大変、風呂にも入れないぐらいで。まぁずっとなんか、受け入れる、YouTubeを見るとか、そういうのはやっていたけど。文字も書けなかったぐらいですからね。
(石山蓮華)なんか私がこの『選挙と鬱』っていう映画を見て、青柳監督のその姿勢に対して、いいなと思ったのが、この『選挙と鬱』っていう事を並べて映画にするために、被写体というか、撮っている相手っていうのが選挙で頑張った事をキッカケになのかわからないですけど、鬱の状態になった時に、映画とその人そのものっていう2つの天秤にかけるべきではないんですけれど、2つの要素があった時に、相手の人生というか、その水道橋博士という人を尊重した上で、映画もちゃんと仕上げているっていうところが、やっぱドキュメンタリー映画のカメラって人をこう傷つける可能性を常に持ってると思うんですけれど、そのカメラを向ける事の怖さというか、気をつけている事とかって青柳さんはどう思ってるのかな?っていうのをぜひ伺いたかったんです。
カメラを向ける事の怖さ
(青柳拓)いやぁ本当だからこれは難しくって。鬱病っていうもの自体も本当に1人、博士のケースっていうもので、それぞれ、色々なパターンもあったり。で鬱になる原因っていうのも1つ原因があったりだとか、複数、複合的なものだったりとか、サイクルであったりとか、そうやって、1つに決められない。で、映画である、第三者である立場から何かこれがきっかけであるって断言もしにくいっていう状況の中で、またカメラを向けるっていう事だけではなくて映画を撮りたいっていう意思を博士に伝えるって事だけでも、博士はエンターテイナーですから、表に出てくる。これ自体が本当の鬱なのかっていう事も分からなくなってくる。まぁカメラの前に立てるっていう事は、それは本当なの?っていう事も、分からなくなってくる。で、実際やっぱ連絡が取れなかったっていう事もあって。なんて言うんだろう、その鬱の輪郭を映画で表現できないかなっていう意識で後半は撮っていきましたね。
(水道橋博士)周りの人のインタビューとかね。
(青柳拓)周りの人のインタビューとか。そうやって核の部分は、やっぱりカメラは何かしら行くっていう方法もあるんですけど。そこは輪郭の方をちょっと今回選びました。
(石山蓮華)私は今この選挙をきっかけにっていうような言い方をしてしまったのは誤りだったなと思ったんですけど、すいません。なんですけど、やっぱりその輪郭を撮るってなかなか簡単じゃないというか。
(青柳拓)簡単じゃないですね。
(石山蓮華)ドキュメンタリー映画であっても、そうじゃない劇映画であっても、その起こっている事を撮るのが1番簡単だと思うんですけど、輪郭を撮るっていうのは、どういう風にものを撮る事なんですか?
(青柳拓)いやどうですかね。でも、自分が悩んでいる事そのままを結構しどろもどろなインタビューとかもあるんですけど。ちょっと自分も泣いちゃっているようなところもポロッとあるんですけど。そういうなんていうか自分のわからなさ含めて見せていく?結構正直にさらけ出しながら出していくっていう事で、だんだんだんだん見えていく可能性がある。そしてあとは周りの人たちがどう思ってるかとか、ご家族、奥さんのチエさんがどう思ってるかとか、そういう事も含めて周りになるべく聞いていくっていう事から、その輪郭が描けるんじゃないかっていうまぁ希望ですね。自分は描けてるっていう意識というよりは、指向性を向けてるって感じですかね。
(でか美ちゃん)なんかでも、やっぱ青柳監督がすごいなと思ったのが、輪郭を撮った上で、やっぱり人間とか病とか、その選挙、政治というものは、本来複雑じゃないですか。政治家も人間がやってるから複雑な色んな思いがあって、分かりやすく政策を打ち出して、なんとか当選に向けて頑張るっていう物語がある上で、途中で、選挙に勝つならこうした方がいいですよっていう、アドバイザーの方が出てくるシーンがすごい好きで。あそこのシーンがすごい、良くも悪くもショッキングな部分だったんで、寄せさせてもらったコメントにも、選挙カーのような感じで、水道橋博士、水道橋博士でございます。『選挙と鬱』、ぜひご覧くださいっていう、そのちょっとまぁ言ったら中身のない文章を最初に書いて、本当は中身が面白いのにっていう一文を添えるコメントを出させてもらったんですけども。
(青柳拓)おもしろいコメント。(笑)
選挙ハック
(でか美ちゃん)その選挙ハックっていうものがあるってわかってたけど、ここまでわかりやすくあるんだって思いましたし、私ちょっと個人的な体験としては本当、ついこの間の都議選の時に、普通に大人の1人として、投票に行きましょうというような発信を自分のSNSに書いたら、ものすごい数のリポストとか、あとコメントをくださる方がいて、それはこう政治関心が高まってて良い事だなと思ったんですけど、まぁ自分とは考え方が異なってるなという人達からも、たくさんリポストしていただいて、ちょっと正直不安に思ったのが、ここの支持者って見えるようになってない?っていう。その、私的には、この政党の1番としている政策はちょっと差別なんじゃないかって思う部分もあるぐらい、なんか反対なところから、反対の支持者の方から、たくさんリポストされる事で、ここの感じに見えないというか。
でも別に誰も悪い事はしてないんですよ。で、むしろその投票に行きましょうって促しではあるし。このリポストも映画で見た選挙ハックの1つなんだとしたら、自分が1番なんとか正直、ちょっと消去法みたいな部分もありつつ、支持している場所、投票した場所が、やってこなかった選挙ハックでもあるなと思ったし。なんか選ばなかった努力っていうのを選挙ハックとしてやってる政党がこんなにも多いんだっていうのを、映画で感じたばっかだったんで。まぁ正直な話ちょっとぞっとする思いもあって、なんかショックだったんですよね。あのシーンがかなり。
(青柳拓)そうですね。でも僕もやっぱり疑問ありますね。選挙システムって結構認知度が広がるってだけでかなり戦局を左右するっていう。政策的な本質的な部分って全然やっぱ語られないですし。クソ暑い夏にやるっていうので誰も聞けないですよね。名前しか。なんかそういう仕組み・システムみたいな事にはすごい疑問を持ちましたね。
(水道橋博士)あと放送でできないっていう事もね。この選挙期間中にこの話や話し合いができないっていうのが、やっぱ人間って全員が政治的なのに、すごく日本人は政治を語るのが下手になっていきますよね。本来語るべき時期に語らないから。
(青柳拓)本当ですね。
(町山智浩)だから大きなテレビとかラジオのとかのメディアが政治というか、まぁ選挙期間中に選挙について報道しないという日本の姿勢ってこれ最近始まったもので。僕が子供の頃は違いますからね。はっきり言うと、第2次安倍政権からこうなってるんですけど。そうなってくと、要するに選挙についての情報というのはネットしかなくなるんですけど、ネットは野放しですから、まったくファクトチェックされていないものが広がっていくんで、投票率が伸びてもそれがいい政治家を選ぶとは限らなくて。ただ、票を稼ぐテクニックを持つものだけが勝つっていう事態に現在なってるんですけど。まぁそういう事は置いておいて、この映画は実はそういう事を話しても『選挙と鬱』っていう映画が難しい映画に聞こえるんですが、この映画はコメディです!
(でか美ちゃん)あっ!出た!伝家の宝刀、コメディです!(笑)
(石山蓮華)町山さんの!コメディ。
(町山智浩)この映画は、コメディです!
(でか美ちゃん)でも見てるんでわかりますコメディですね。
(石山蓮華)そうなんですよ。これはね、なんかタイトルだけ見るとかなりね、この画数、鬱って多いしドキッとするんですけど、楽しく見られました。それはやっぱり監督のこの人柄というか撮り方もそうですし、被写体が博士であるっていう事がすごく大きかったんだと思うんですけれど。改めてその博士にとって、この作品ご覧になってどんな感想を持ちましたか?
(水道橋博士)僕はドキュメンタリー自体も大好きだし評論もいくつも書いてるけど。だからそういうサシャ・バロン・コーエンであるとかマイケル・ムーアとかすごく影響があって、そういう政治を舞台にしたコメディ的なドキュメンタリーをなぜ作らないんだと思っていたので、自分自身が主役でこれが撮れるんだって、そしてカメラマンを得て、自分の中ではもう主人公として伸び伸び選挙の部分はやってて、本当に楽しいです。楽しいし、面白いシーンがいっぱいあると思います。あれは僕しかできないなと思いましたから。
(青柳拓)そうですね。
(でか美ちゃん)明らかにその政治家になるべく出馬してるんですけど、完全に芸人の顔が出ちゃってる時もめっちゃあって。こう言っちゃあれなんですけども、青柳監督こんなニコニコして、見る人が見たら炎上するかもみたいなシーンもバンバン入れてるんですよ。鋭く。
(石山蓮華)そうですね。であのMe, Weって。あたなは私、私はあなたってっていう事を博士がこの選挙のスタートから標語として言ってますけれど、それが本当にハマる作品にどんどんなっていったんだなと思いました。そして、もうお時間そろそろになってきますかね、最後になってしまうんですが、監督とそして博士からリスナーさんにメッセージをお願いします。
(青柳拓)はい。じゃぁ僕からでいい・・?はい。でも選挙っていうものがテーマの映画なんですけど、気がついたらその自分の話として見てしまうような、そんな不思議な体験をこのドキュメンタリーでできます。笑っていいとこ、笑うところもすっごい多いですし、最後にはちょっと胸に残るものもあると思うのでぜひ皆さん、劇場に今週末から公開です。見に来てください。お願いします!
(水道橋博士)はい。僕も6月28日公開なんで。映画興行っていうのも選挙にすごく似てるんですね。だから1票1票積み重ねていく事だし、とにかく初期、最初に入れないと長くできないとか、勝ち負けがあったりするので。これはもうみんなで、僕らゲリラ戦を戦っている気持ちでやってるので、ぜひぜひ応援していただければと思ってます。
(青柳拓)1票をお願いします!
(石山蓮華)そうですね。(笑)チケットが1票になります。そして町山さん、改めてこの映画、どんな人に見てほしいなと思いますか?
(町山智浩)もう本当、誰でもいいんです。とにかくこの映画ね、政治に全く興味なくても、1分先の展開が予測できないというですね、ええっ?っていうのが延々と続きますので。ただ、楽しんでもらえればいいと思います。
(水道橋博士)マスコミ試写でも拍手が続くんですよ。これはもうすごい意外でした。
(青柳拓)なかなかない事ですよね。
(でか美ちゃん)あとその町山さんも博士もいらっしゃってっていう、同席して自分もいるという場が初めてなんで、改めて映画と関係ない事を言いたいんですけど。マジお互いの友情関係大事にしてて。本当にここは。同い年ぐらいの、博士最近若い人と仲いいから、同い年ぐらいの友情マジでもう見ててなんかグッとくるんで。たまになんか生配信でケンカみたいなっているんで。(笑)
(町山智浩)みんなするんです。この年だと。(笑)
(でか美ちゃん)それが伝えられただけで私は十分です。
(石山蓮華)という事で今週28日土曜日から公開される映画、『選挙と鬱』から、映画の主演である水道橋博士と青柳拓監督にお越しいただきました。水道橋博士、青柳監督お2人ともありがとうございました。
(青柳拓)ありがとうございました。
(石山蓮華)町山さんもありがとうございました。
(町山智浩)どもでした!
※書き起こし終わり
○○に入る言葉のこたえ
③水道橋博士の2022年の選挙を追ったドキュメンタリー映画